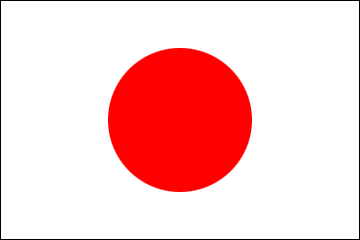伊藤秀樹大使 着任3年目のご挨拶
平成28年9月5日
皆様、いかがお過ごしでしょうか。駐スーダン大使の伊藤秀樹です。
私が初めてスーダンを訪れたのは、1981年、まだ研修生としてエジプトでアラビア語を勉強していた時でした。当時のハルツームは、こぢんまりとした小さな町で、空港の周りも閑散としていました。舗装はまばらで、ナイル川、緑の葉を繁らせた木々、そして赤い土のコントラストがいかにもアフリカらしく、今でも印象に残っています。それから30年以上を経て、再び目にしたハルツームは、町も格段に大きくなり、近代的な高層ビルも、そこかしこに見られました。
早いもので、私がスーダンに赴任してから2年が経ちました。この間、日本政府は、農業開発、基礎生活分野、平和の定着の三つの分野を中心にスーダンを支援し、日・スーダン間の友好関係を維持、発展させてきました。
農業開発については、稲作支援や灌漑ポンプ場の建設を行うことで食糧生産の基盤を整備し、貧困の削減と、食糧安全保障の実現を支援してきました。農業はスーダンの基幹産業であり、日本が支援している米や大豆は、スーダンの経済成長を担う品目として期待されています。
基礎生活分野としては、まず、保健医療において、日本が長年にわたり支援してきている村落助産師の訓練に加え、ハルツーム郊外の病院に母子病棟を建設しています。また、水供給事業を強化するため、州水公社の運営を指導し、白ナイル州コスティに浄水場を建設します。首都ハルツームでは、ゴミ収集車を提供するとともに、その整備工場も建設し、さらに定時定点というゴミ収集法を指導し、環境美化を推進しています。加えて、職業訓練にも力を入れて、就業率の改善にも取り組んできました。
残念ながら、スーダンでは、大量の紛争被災民や近隣諸国からの難民が発生しています。日本政府は、食糧支援、地雷除去、武装解除・動員解除・社会復帰などを含めて、旧紛争地域での生活環境を整備することで、平和の定着を支援しています。
「単に魚を与えるのではなく、魚の釣り方を伝授する」べく、長期的な視野に立った人材育成や技術移転を重視し、スーダンの持続的で自立的な発展に寄与する日本の支援は、スーダン政府や国民から高く評価されています。
スーダン人は、また、日本のアニメやマンガなどのポップカルチャー、折り紙や生け花等の伝統文化、柔道や空手といった日本の武道に、強い興味を持っています。国費留学生やABEイニシアティブ、更に短期の研修を加えれば、これまでに何百人ものスーダン人が日本を訪れる機会を得ています。目下、スーダン人レスリング選手が2020年の東京オリンピックに出場できるよう、両国間で協力し合っています。
先般、ケニアで第6回アフリカ開発会議(TICAD VI)が開催されました。その際、ガンドゥール・スーダン外相が、岸田外務大臣と会談を行いました。席上、ガンドゥール外相からは、日本の支援に対する謝意が表明されました。日本政府は、スーダンの地政学上の役割を重視しており、スーダンとの関係をより強化させてゆきたい旨、伝えました。
他方、国際社会におけるスーダンのイメージは、決して芳しくありません。スーダン政府が進めている国民対話が、真に包括的な形で実現し、国際社会におけるイメージが前向きに変化することを期待し、日本も可能な働きかけを行っています。
これまで、私はスーダンの地方を積極的に訪問し、日本の支援をスーダン国民の方々に伝えてきました。どこに行っても、政府高官から地域の人々までが、皆、歓喜の声で迎えてくれます。スーダンは、アフリカで3番目に大きい国で、日本の5倍の国土があり、地方の訪問は必ずしも容易ではありませんが、今後も、スーダンの各地を訪れて、日本の考え方をスーダン国民に伝え、スーダン国民との友好関係の強化に努めてゆく所存です。
最後になりましたが、皆様のご多幸を祈念するとともに、日・スーダン間の関係発展のため、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
私が初めてスーダンを訪れたのは、1981年、まだ研修生としてエジプトでアラビア語を勉強していた時でした。当時のハルツームは、こぢんまりとした小さな町で、空港の周りも閑散としていました。舗装はまばらで、ナイル川、緑の葉を繁らせた木々、そして赤い土のコントラストがいかにもアフリカらしく、今でも印象に残っています。それから30年以上を経て、再び目にしたハルツームは、町も格段に大きくなり、近代的な高層ビルも、そこかしこに見られました。
早いもので、私がスーダンに赴任してから2年が経ちました。この間、日本政府は、農業開発、基礎生活分野、平和の定着の三つの分野を中心にスーダンを支援し、日・スーダン間の友好関係を維持、発展させてきました。
農業開発については、稲作支援や灌漑ポンプ場の建設を行うことで食糧生産の基盤を整備し、貧困の削減と、食糧安全保障の実現を支援してきました。農業はスーダンの基幹産業であり、日本が支援している米や大豆は、スーダンの経済成長を担う品目として期待されています。
基礎生活分野としては、まず、保健医療において、日本が長年にわたり支援してきている村落助産師の訓練に加え、ハルツーム郊外の病院に母子病棟を建設しています。また、水供給事業を強化するため、州水公社の運営を指導し、白ナイル州コスティに浄水場を建設します。首都ハルツームでは、ゴミ収集車を提供するとともに、その整備工場も建設し、さらに定時定点というゴミ収集法を指導し、環境美化を推進しています。加えて、職業訓練にも力を入れて、就業率の改善にも取り組んできました。
残念ながら、スーダンでは、大量の紛争被災民や近隣諸国からの難民が発生しています。日本政府は、食糧支援、地雷除去、武装解除・動員解除・社会復帰などを含めて、旧紛争地域での生活環境を整備することで、平和の定着を支援しています。
「単に魚を与えるのではなく、魚の釣り方を伝授する」べく、長期的な視野に立った人材育成や技術移転を重視し、スーダンの持続的で自立的な発展に寄与する日本の支援は、スーダン政府や国民から高く評価されています。
スーダン人は、また、日本のアニメやマンガなどのポップカルチャー、折り紙や生け花等の伝統文化、柔道や空手といった日本の武道に、強い興味を持っています。国費留学生やABEイニシアティブ、更に短期の研修を加えれば、これまでに何百人ものスーダン人が日本を訪れる機会を得ています。目下、スーダン人レスリング選手が2020年の東京オリンピックに出場できるよう、両国間で協力し合っています。
先般、ケニアで第6回アフリカ開発会議(TICAD VI)が開催されました。その際、ガンドゥール・スーダン外相が、岸田外務大臣と会談を行いました。席上、ガンドゥール外相からは、日本の支援に対する謝意が表明されました。日本政府は、スーダンの地政学上の役割を重視しており、スーダンとの関係をより強化させてゆきたい旨、伝えました。
他方、国際社会におけるスーダンのイメージは、決して芳しくありません。スーダン政府が進めている国民対話が、真に包括的な形で実現し、国際社会におけるイメージが前向きに変化することを期待し、日本も可能な働きかけを行っています。
これまで、私はスーダンの地方を積極的に訪問し、日本の支援をスーダン国民の方々に伝えてきました。どこに行っても、政府高官から地域の人々までが、皆、歓喜の声で迎えてくれます。スーダンは、アフリカで3番目に大きい国で、日本の5倍の国土があり、地方の訪問は必ずしも容易ではありませんが、今後も、スーダンの各地を訪れて、日本の考え方をスーダン国民に伝え、スーダン国民との友好関係の強化に努めてゆく所存です。
最後になりましたが、皆様のご多幸を祈念するとともに、日・スーダン間の関係発展のため、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。